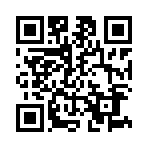2017年08月04日
今度の貸切で使う装備品
いろんな人から着想を得てあたらしい装備品を作りました。
今度の貸切サバゲではスポンジ刀を使ってよいとのことなので私はSAMURAIになります。


こんにちは。4年生のNJRです。




ふだんはふざけた格好のニンジャ装束でサバゲをしています。
〈はじめに〉
ニンジャ装束の運用開始からおよそ1年半が経ちました。
セーフティエリアにいるときには頭巾と面頬と籠手を外しているので、筒袖と袴だけを着ているわけですが、
そこを通りかかったフィールドスタッフに「剣士みたい」とか「武士みたい」とか言われることが2~3回ありました。
こちとらNINJAだぞ、NINJUTSUを使うぞ、と内心思ってたのですけれども、
この度ふだんの装束の上から着けられる「武士オプションパーツセット」を作りました。
なお、今回の装備づくりはいろいろと超解釈をしているので
平安~戦国期の甲冑をご専門にしていらっしゃる方などが心の健康を損なわれましても
此方では責任を負いかねますのであらかじめごりかいください。
サバゲの世界では、鎧武者の姿でゲームをされる方はもうすでに多くいらっしゃるので、
正式なお作法にのっとった武士サバゲはその方々におまかせしましょう。
自分は自分なりの「現代の当世具足」を目指したいと思います。
〈どのようなものを作るか〉
さて、武士オプションパーツセットを作るにあたって、まずはコンセプトを明確にします。
コンセプトは「サバゲ用の」甲冑です。銃撃戦用の甲冑じゃありません。
全身ヒット制のサバゲでは装甲は飾りであってロマンであるのです。
また、1から甲冑を作るにはかなりの労力が必要なので、身の回りにあるものを改造して作ります。
具体的には帽子を兜に、チェストリグを腹巻にします。
装甲板にはふつう甲冑には漆を塗った革や鉄板を使用しますが、軽量化と高機動化のためにポリエステルの合皮を使います。
〈甲冑の要素とサバゲの要素〉
全体的な形状の規範とするのは、南北朝時代あたりの歩兵の装備を参考にします。
中世日本の戦いは弓箭が主体でありました。太刀や剣などの打物も身に着けてはいましたが、
打物が主役となるのはもっと後の時代のようです。
飛び道具の時代の甲冑こそ、サバゲで使うにはふさわしいのではないでしょうか。
甲冑のおもな構成パーツに札(さね)と呼ばれるものがあります。
中世の甲冑は小札(こざね)という小片をつなぎ合わせて装甲が形作られています。
しかしながらこの小札はあまりにもコストがかかりすぎるので、戦国時代の主流である板札(いたざね)を組み合わせます。
板札は横に細長いので、縦につなげていくことで小札を使うよりコストを抑えることができます。
札を紐でつなぎ合わせることを縅す(おどす)と言い、それで使う紐のことを縅毛(おどしげ)と呼びます。
今回はポリエステルの紐を使います。紐の組み方にもいろいろな種類がありますが、
最もシンプルな素掛縅(すがけおどし)を採用しました。
縅毛は、甲冑の名前を決めるときの要素のひとつになります。
赤い紐を使えば「赤糸縅」、黒いなめし革を使えば「黒韋縅」となります。
今回使うのは青い紐なので「青糸縅」になります。
青にした理由は、サバゲにおいてチーム分けの色となる赤や黄色に見間違えられないようにするためです。
では、以上をふまえて甲冑を形にして行きましょう。
〈兜〉

ナイロンとポリエステルのメッシュキャップに、首回りを防御する錣(しころ)がついています。
平安や鎌倉風の大きな吹き返しは被弾面積が増えるので最小限に抑えました。
錣はスナップボタンで取り外しができるようにしたので持ち運びにも便利です。
前立ては虹色に変化するビニールを切り出しました。
モチーフは麻の葉です。麻は古代から衣服の原料として重宝された植物です。
日本神話にも天照大神の衣としての記述もあり、神聖なものでもあります。
麻の繊維は高い強度を持つので、堅い守りの象徴とすることができるでしょう。
(薬理作用をもつ大麻と混同されがちですが、現在は品種改良によって繊維用のヘンプと
薬事利用のカンナビスというように区別がされています。
日本では大麻取締法により大麻の所持、使用は禁じられています。薬物の乱用は絶対にやめましょう。)
〈腹巻〉

そもそもチェストリグには防具としての役割はないのでプレートキャリアとかを使ったほうがいいと思うのですが
そういったものは持ってないのでチェストリグを使います。
正面にバイタルゾーンを防御する栴檀板(せんだんのいた)・鳩尾板(きゅうびのいた)をつけました。

こちらは背中側です。全くもって装甲がありません。防具としては大問題です。
左側面に射向袖(いむけのそで)をつけました。
右側に来る馬手袖(めてのそで)はショットガンのスリングと干渉してしまうため外しました。
本来の甲冑でも弓箭主体の合戦では射向袖の方がより重視されていたようです。
〈半籠手〉

ニンジャ用とは別に籠手を作りました。
「実力行使」のビニール籠手は今年の冬に作ったもので
すでに1度実戦投入されていくつかの弾痕があります。
腕の内側部分を伸縮性のある紐で編んであるのでひじから先だけで固定することができます。
〈おわりに〉
まだまだ甲冑としては不十分な部分が多く残りました。
熱中症になりたくないので涼しくなるまでこれ以上のパーツ追加は一旦やめます。
今後の課題としては、喉輪の追加やヒップバックホルスターに干渉しないMOLLEベルト対応の草摺を作ることです。
それでは部員のみなさんは今度の貸切ゲームでお会いしましょう。
Posted by 日法鯖研 at 11:09│Comments(0)
│装備紹介